バイオセンサー研究室
秋元卓央 教授
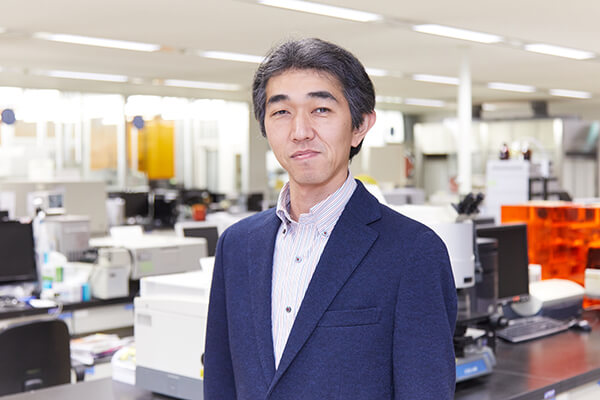
微生物を利用した環境汚染物質を測定するバイオセンサーの開発を行っています。対象は地雷、変異原物質、農薬、Biochemical Oxygen demand (BOD)です。例えば地雷を測定する場合、トリニトロトルエンに応答して蛍光色が変化する微生物を作製します。この微生物を地雷の存在が疑われる地域に散布すると、地雷のある場所と無い場所で微生物の蛍光色が変化するため、地雷の存在を微生物の蛍光色で判断することができます。農薬は、農薬を分解する特殊な酵素の遺伝子と蛍光タンパク質の遺伝子の両方を持つ微生物を作製し、この微生物を利用して測定します。この場合も微生物の蛍光色が変化することで農薬を測定することができます。他の境汚染物質でも同様に、本研究室では微生物の蛍光色の変化などで環境汚染物質を検出することを目指しています。
水環境工学研究室
浦瀬太郎 教授

後藤早希 助教

水環境工学(浦瀬太郎・後藤早希)研究室では、生活や産業に欠かせない水の問題やそれに関連した微生物について研究しています。(1) 膜分離技術や微生物を用いた廃水処理技術、(2) マイクロプラスチック問題、(3) 医薬品の使用に伴う薬剤耐性菌の水環境での広がり、(4) バイオプラスチックの生産、の各課題を生物や化学に関連した最新技術を用いて掘り下げます。この研究室では、個人の健康や個人の快適をベースとしながらも、社会として豊かになる、社会として快適になることを目指しています。たとえば、抗生物質の使用は個人を細菌感染から守りますが、耐性菌の広がりという社会的マイナス面も生じます。純粋な「理科」として問題をとらえるだけでなく、「社会」を含んだアプローチを重視しています。多くの卒業生が、上下水道の水質管理や環境分析コンサルタント業の分野(民間企業および公務員)で活躍しています。
植物工学研究室
多田雄一 教授
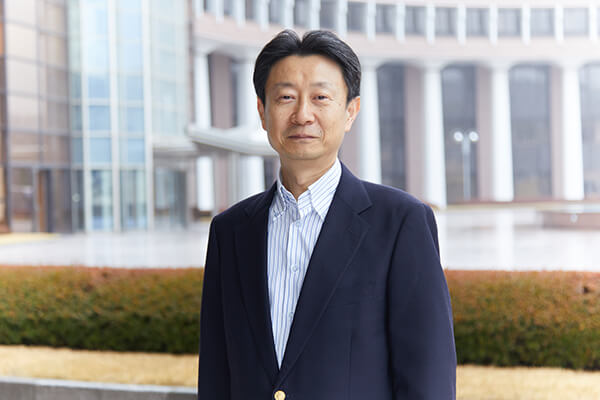
鈴木洋弥 助教

植物の力を地球環境の保全や私たちの暮らしを豊かにするために役立てる植物バイオテクノロジーの研究を行なっています。特に、一部の植物が海水や高温に耐える仕組みを解明・利用して、作物の耐塩性や高温耐性を向上させることを目指しています。これらは温暖化対策や環境保全に役立ちます。また、植物の肥料成分であるリン酸やカリウムを吸収・輸送する能力を強化して、肥料が不要な植物を開発する研究も行っています。肥料が不要な作物の開発は、途上国の食糧生産を高めるとともに、施肥による環境汚染の防止にも役立ちます。また、リン酸肥料の原料であるリン鉱石の枯渇問題の解決にも貢献します。他にも、植物が空気中の有害物質を吸収・浄化する機能を高める研究、甘いイチゴをつくるなど農産物の付加価値を高める研究も行っています。研究成果は、食糧不足、砂漠緑化、環境負荷問題の解決につながり、いくつかのSDGsの達成に貢献します。
バイオプロセス工学研究室
松井徹 教授

化学品、食品、医薬品、化粧品などに使用する材料の生産や、環境浄化をするために微生物機能を利用することを目的として、環境中からの微生物探索、機能解析、大量生産条件検討などを行い、バイオプロセスを構築する。また、産業に活用するための微生物資源ライブラリーの構築も併せて行う。