応用生体科学研究室
矢野和義 教授

病気の早期診断・早期治療に貢献できるようなバイオテクノロジーの確立を目指しています。まず、抗体のような分子認識能を持ち標的分子に特異的に結合できる特殊なDNA(アプタマー)を開発し、病気の診断や病原性微生物の検出に応用することを目指しています。疾病のターゲットとしては、免疫不全状態となるAIDSの進行度を測るための指標となる免疫細胞表面のタンパク質や、院内感染を引き起こす黄色ブドウ球菌などです。また、病気を見つけ出す抗体やDNAアプタマーを多数貼り付けたガラス基板(抗体チップ、アプタマーチップ)を作製し、複数の病気の指標成分を一度に検出することにもチャレンジしています。このときにナノテクノロジーを駆使して極めて薄い膜(ナノ薄膜)をあらかじめガラス基板に作製しておくことで、目的の成分を高感度に検出することが可能となります。
細胞酸化ストレス研究室
加柴美里 教授

岡本瑞穂 助教

加齢や様々な病気の原因として活性酸素が注目されています。活性酸素は、わかりやすくいうと酸素が高い反応性を獲得した形のことで、活性酸素が生体内の脂質やタンパク質・核酸を傷つけてしまうことが加齢や病気に関係していると考えられています。 当研究室では、活性酸素を消去する抗酸化物質に注目しています。 具体的な研究テーマとしては ①細胞中の主な活性酸素産生サイトであるミトコンドリアの呼吸鎖超複合体の中に含まれるコエンザイムQ10の解析。②脂溶性のコエンザイムQ10と結合してこれを可溶化する蛋白質の機能解析。③メダカを用いた受精と抗酸化物質の関係の解明。④神経細胞のコエンザイムQ10量を増やす手法の開発、などです。 本研究により、老化をとめたり、病気の発生を抑制する手掛かりを得たいと思います。
生体機能化学研究室
加藤輝 教授
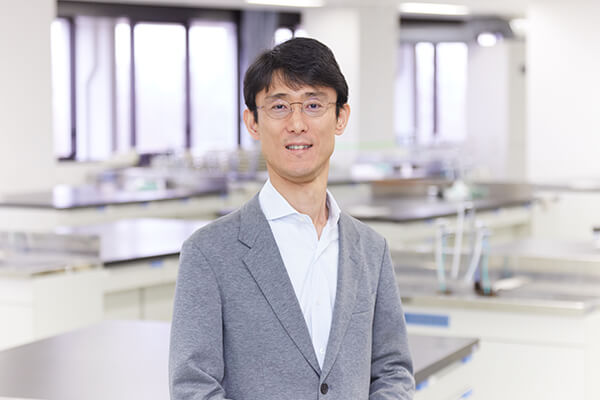
ユニークな機能を持つDNAやRNAを作製し、新たな診断技術や、細胞表面および細胞内物質の可視化技術、さらには、創薬に利用する研究を行っています。例えば、蛍光タンパク質のように蛍光を発するDNAやRNAを作製し、これらの様々な利用法を研究しています。具体的には、がんのマーカー(目印)タンパク質や疾患に関連するRNAなどの細胞内物質に結合すると、それらを検知して蛍光を発する機能性RNAを開発し、がん細胞の種類を迅速に判定する診断技術や、新しい医薬品のスクリーニング(探索)技術への利用を目指しています。さらに、がんなどの早期発見を目的とした遺伝子診断法として、“メチル化”などの遺伝子の化学的修飾を迅速に検出する方法を開発しています。
生物創薬研究室
佐藤淳 教授
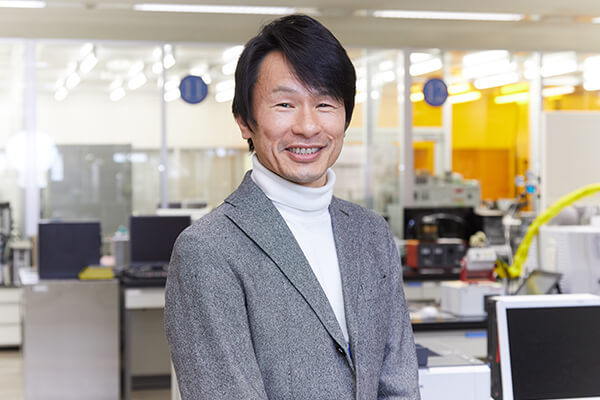
木村将大 助教
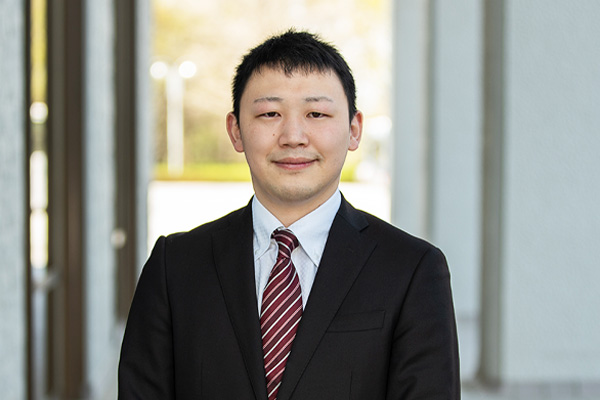
遺伝子組換え、生物工学、細胞培養技術を基盤とするバイオ医薬品に関する研究を行っています。自然免疫で機能するタンパク質であるラクトフェリン (LF) に着目し、その機能解析(特に抗腫瘍)を進めるとともに、その創薬化をバイオベンチャー企業と共同で進めています。ヒトIgG Fcやヒトアルブミン(HSA)を融合させることにより、LFの体内安定化に成功しました。LF/ヒトIgG Fc融合タンパク質は、副作用の可能性となる免疫エフェクター機能を示さない新規製剤であり、自己免疫性の肝炎動物モデルでその有効性が確認されました。LFはHSAと融合させることで、ある種のガン細胞に対して増強した増殖阻害を示すことを見出し、抗ガン剤としての開発を進めています。機能性ペプチド研究に関しては、研究室で開発したスクリーニング法 (MOPS法)を駆使し、ファージディスプレイペプチドライブラリーからの医薬品シーズの創製を目指しています。
機能性RNA工学研究室
杉山友康 教授
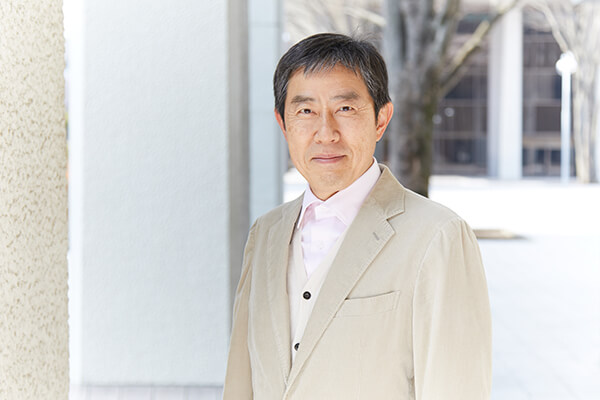
遺伝子の働きをノックダウンする独自技術を中核として、核酸医薬の探索、遺伝子の新しい機能解明、細胞の制御、モデル動物の解析等によって新しい核酸医薬の創製を目指します。また、新属新種の細菌 Flexivirga albaを解析して、土壌環境汚染の浄化に寄与する技術開発を目指します。
腫瘍分子遺伝学研究室
村上優子 教授

がん(特に悪性中皮腫)を対象に、がんの分子病態の解明を通して、新規分子標的・血中循環がん細胞検出法・腫瘍マーカー・新規がん抗原の開発への貢献を目指しています。 手法としては、遺伝学、分子生物学、生化学を用い、系としては培養細胞、マウス、モデル生物を利用します。 また、低分子化合物のスクリーニング、核酸医薬の開発も共同研究で行なっています。
応用生化学・ヘルスケア工学研究室
横山憲二 教授

次世代ヘルスケア産業に貢献する技術開発を行っています。これまでに、①血糖値センサーに使用する新規耐熱酵素FADグルコース脱水素酵素の探索・改変、②高機能ヘルスケアセンサーチップの開発(レドックス活性高分子を用いた連続測定型血糖値センサー、NADHの電気化学反応の解析とケトン体センサー、乳酸センサーへの応用)、③血液透析装置に実装するためのセンサーの開発(酸化型/還元型アルブミン比の電気化学センシング)、④食品、化粧品成分のHPLC分析(電気化学活性種ラベル化によるアミノ酸、界面活性剤、化粧品成分の分析、イオンペアクロマトグラフィーによるビタミンC誘導体の分析)、⑤抗酸化物質の活性評価などに関する研究を行っています。
エピジェネティック工学研究室
吉田亘 教授

「第5の塩基」と呼ばれるメチルシトシンと、DNAの特殊構造である四重鎖構造に着目し、がんを簡便に診断できる技術や、医薬品開発に向けた基礎研究に取り組んでおります。メチルシトシンは遺伝子の発現を制御する遺伝子スイッチとして機能しております。がん細胞などの異常な細胞ではこの遺伝子スイッチ状態が異常になるため、これを検査すれば簡単にがんを診断することが可能です。本研究室では遺伝子工学を駆使して人工タンパク質を創り出し、新たなメチルシトシン検出方法を開発しております。また、DNAは通常二重らせん構造を形成しますが、特定の配列を持つDNAは四重鎖構造と呼ばれる特殊な高次構造を形成します。本研究室ではこの四重鎖構造に着目し、ヒトゲノムDNA中で四重鎖構造が形成される領域やその機能を明らかにし、医薬品の新たな標的を同定する研究に取り組んでおります。
バイオインフォマティクス研究室
土井晃一郎 准教授

コンピュータを用いて生物学の研究を行うドライ系の研究室です。近年の生物学の研究から生み出され、蓄積されているDNA塩基配列などのデータの量は莫大です。そして、今後も更に大量のデータが生み出されてきています。このような大規模で多様なデータを活用して生物学、医療に有用な知見を得るにはコンピュータの力が不可欠です。また、単にコンピュータを使うだけではなく高速で性能のよい計算手法を考えなくてはいけません。我々は大量のゲノム配列などの生命データに対応するため、それらを処理するアルゴリズム、データマイニング手法の研究開発を行っています。また、生物実験系の研究者に役立つ研究開発を目指して、実際の生命、医療データに対する応用を行っています。
分子生物学研究室
西良太郎 准教授

遺伝情報が保存されているゲノムDNAの恒常性の維持は生命にとって必須です。しかしながら、ゲノムDNAは、紫外線などの外的な要因やDNA複製のエラーなどの内的な要因により常に傷(DNA損傷)を受けています。生物は多様なDNA修復機構により、タイプの異なるDNA損傷を修復し、DNA損傷に起因する有害な事象を防いでいます。発生したDNA損傷が修復されなかった場合や、不適切な修復が行われた場合には、細胞死、細胞のがん化が誘発されることが知られており、DNA修復機構が生物にとって重要な役割を果たしていることは明らかです。 本研究室では、主にヒト細胞を用いて、DNA損傷のうち電離放射線や抗がん剤等により生じるDNA損傷であるDNA二本鎖切断(DNA double-strand breaks: DSBs)の修復機構の解明をおこなっています。最終的にはDSBの修復機構を理解し、がん細胞においてのみDSB修復を阻害することで、より効果的で安全ながんの放射線・化学治療の確立を目指しています。